みなさんこんにちは!美琴です✨
今回は、世界2位の体長を誇るカッコよくて人気のクワガタ、マンディブラリスフタマタクワガタの幼虫飼育についての記事です✨
私美琴はマンディブラリスが大好きで、我が家では2亜種(スマトラ、ボルネオ)を育てています。
最近になって幼虫たちが数十匹単位で大量羽化してきました!!
たくさんの幼虫たちを育ててきて今読者のみなさんに心から伝えたいことがあります。
それは、
せっかくマンディブラリスを育てるのならデカく育ててほしい
ということ。
小さい成虫もミニチュアフィギュアみたいで味もあるにはあるんですが、
やはり本種の魅力を最大限引き出すには大きく育てることに尽きると思うんですよね…
オスで90mmを超えるとやはり迫力が違います。
この記事では、マンディブラリスを大きくするために大事だと私なりに考えたことをまとめましたので、是非、最後まで読んでいただけると嬉しいです!
※そもそもマンディブラリスのブリードってどうするの?と思われた方はこちらをご参照ください!↓
ポイント1:ボトルのサイズアップのタイミングを見逃すな!~マンディブラリスの罠~
はい、まず大事になるのがこちら、
「ボトルのサイズアップのタイミングを見逃すな」
です。
クワガタやカブトムシをある程度飼育した経験のある方からすれば、
「幼虫が大きくなるにつれてボトルのサイズも大きくするのは当たり前でしょ」
と思われたかもしれません(笑)
でも、なんで今更こんなことを言うのか。
それは、
マンディブラリスの幼虫飼育には恐ろしい「罠」があるから
なんですね~
「罠」とは何か。
それは、「気がついたら」小さい容器で幼虫を羽化させていた、という呪いです…😱
何を隠そう、私美琴はあろうことか幼虫たちを小型の1500ccボトルで羽化までもっていくという暴挙に出ていますw(オスもですw)
その結果、みなさんお察しの通り全オスが超小ぶりなサイズで羽化してきちゃいました😭😭😭

ではなぜ美琴は1500ccという小さい容器で幼虫を羽化まで育ててしまったのか。
それは、
マンディブラリスの幼虫は驚くほど成長が遅く、「ボトルのサイズを上げよう!」と一念発起するきっかけが生まれにくいから
なんですね。
そしておそらく、
容量依存の傾向が強く出てくる種
だと思います。
※容量依存=成長度合いが飼育スペースの大きさに影響を受けること
私もマンディブラリスのオスの幼虫を育てるには当然、大きな容量のボトルが必要だと思い、
3000ccのボトルを用意してありました。
私は、1500ccボトルで育てているオスの体重がだいたい20gを超えることがあれば3000ccのボトルへお引っ越しさせようかと悠長に構えていました。
実際、以前インターメディアツヤクワガタやギラファノコギリクワガタ(ケイスケ)といった大型種の幼虫を元々1500ccボトルで育てていましたが、
(特にインターメディアは)どんどん大きくなっていったので「さあ、3000cc以上の容器に移し替えるぞ!」というタイミングが掴みやすかったのです。
インターメディアツヤクワガタの幼虫飼育についての記事はこちらからお読みいただけます✨
しかし、マンディブラリスとくると1500ccのボトルでは全くと言っていいほど成長しませんでした。
当時の私はネットで、大型のマンディブラリスのオス幼虫の最終体重は30g台に乗ることを知識として持っていました。
ですので、30gとはいかないまでも、
「このまま待っていれば体重は伸びてくるんだ」
「成長が緩やかなだけで、きっと幼虫期間は長いだろうから時間をかけてゆっくり大きくなるさ」
と思い込んでいました。
しかしすぐに悲劇は起こりました!
なんと、10g台のオス幼虫たちが次々と蛹室を作り、中で前蛹になり始めたのです…!!!
「いや、早すぎだよ!」と。
でも現実を受け入れられない私は、
「いや、まだ大丈夫。一見すると前蛹サイズは小さいけど、マンディブラリスは自分の体くらいに長い大顎を持つはずだから、トータルの体長自体は稼げるはずだ!」
と考えていました。いや、そうであってくれと必死に願っていました😭
しかし残念なことに蛹になってもオスの顎は伸びず、
「かわいらしい」マンディブラリスが大量に爆誕しました。スマトラ亜種、ボルネオ亜種共にです!
…ここから何が言えるか。
きっとマンディブラリスはインターメディアやギラファなどの他属の大型種と違い、
ある程度狭い容器だと成長の限界を決めてしまうのでしょう。
ですからおそらくですが、
オス幼虫の体重が10g台と小さく、今使ってる容器内でもまだまだ成長できそうだとしても、思い切って大きな容器に移すことが必要なのだと思います。
ちなみに余談ですが、メスについては1500ccのボトルでも、極端に矮小化しませんでした。
まだ測ってはいませんが、40mm台にはしっかり届いてそうです。
メスにとっては1500ccのボトルは成長するにあたり十分な容量(スペース)だったのでしょう。
ポイント2:菌糸ビンのすゝめ
これに関しては賛否両論あるかとは思いますが、
マンディブラリスのオスの幼虫を育てるなら菌糸ビンを使ってみる価値がありそうです。
某昆虫系のインフルエンサーの方がマンディブラリスを結構なサイズで羽化させておられたのを偶然見たのですが、その方は菌糸ビンを使っていらっしゃいました。
また、時系列的に幼虫を育てる前の話になるのですが、
地元の昆虫ショップへ行き、店長さんとマンディブラリスの話題になった時も、
「マンディは菌糸で育てるのがいいよ」とおっしゃっていたんですね。
しかし飼育費用を極力抑えたかった私は、全個体発酵マットで管理していました。(店長さんゴメンナサイ…😭)
素直に菌糸ビン使ってればよかったかも!
次世代を育てるときは気をつけよーっと!!
まとめ
今回の飼育から得た教訓は以下の2つです。
1.早い段階で大きな容器に移す←小さい容器でいつまでも育てているとそこで成長がストップする可能性大
2.菌糸ビンを使う
今私の元には羽化したての2亜種(スマトラ・ボルネオ)のオスとメスたちがたくさんいます。
また繁殖を頑張っていっぱい幼虫を得て、今度こそ大きなオスを羽化させられるようにがんばります!
ここまで読んでくださりありがとうございます(^^)
次回の記事もお楽しみに!
だすびだ〜にゃ⭐️
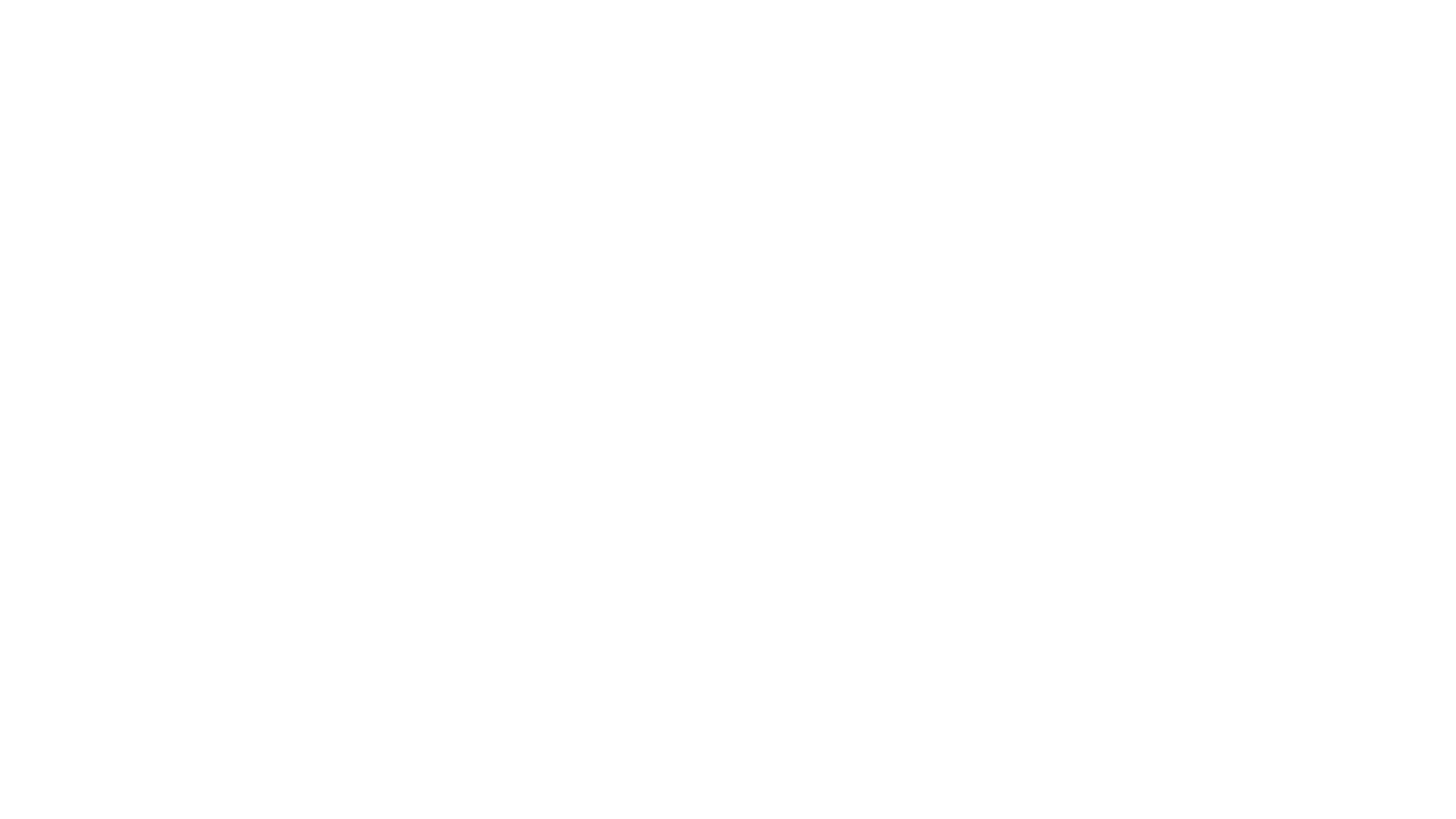








コメント